弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
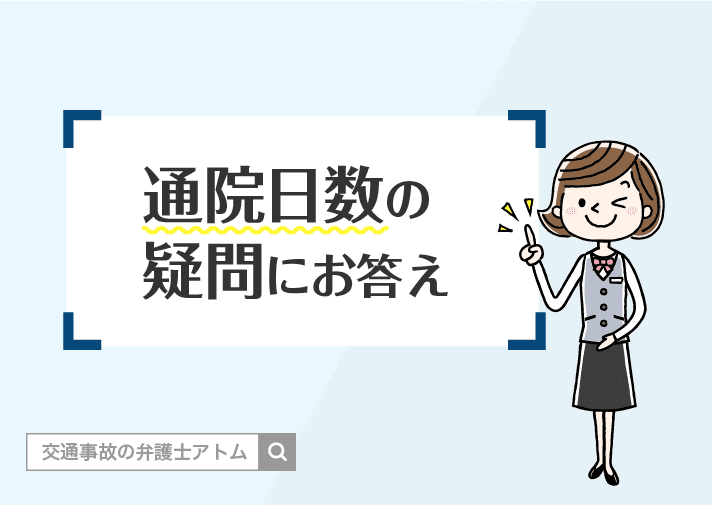
交通事故では、通院日数や頻度によっては賠償請求時に不利になってしまうことがあります。
また、リハビリも治療費として加害者側に負担してもらえるのかも気になるところですよね。
こうした通院日数に関する疑問に、Q&A方式でお答えします。
Q. 通院日数が少ないと、後遺障害等級認定に不利になりますか?
A. 通院頻度が月に1回以下であったり、通院期間が6ヶ月以下であったりすると、不利になる可能性があります。
後遺障害等級認定では、
を証明することが重要です。
通院日数が少ないと、この2点について疑われる可能性があります。
治療期間中に1ヵ月以上通院が途絶えると、交通事故によるけがが治って治療を終了したものの、1ヶ月以上たってから別の原因でけがをしたからまた通院したのではないか?と疑われます。
また、あまりに通院期間が短いと、本当にこれ以上治療をしても回復しないのか?まだ回復の余地はあるのではないか?と疑われやすくなります。
ただし、たとえ治療期間が短くても、医師による医学的な判断に基づいているならば必ずしも6ヶ月以上通院しなければならないというわけではありません。
整骨院への通院は、病院への通院と同じようには扱われない可能性が高いです。
また、整骨院では後遺障害等級認定に必要な診断書を作成してもらえません。
たとえ整骨院に頻度高く通っていたとしても、月に1回は病院にも通っておくことが望ましいです。
整骨院通院に関する詳細はこちらをご覧ください。
Q. むちうちの通院日数には限度があるというのは本当ですか?
A. 通院日数に限度はありませんが、加害者側に治療費を支払ってもらえる日数は90日を限度とされることが多いです。
交通事故に遭った場合、けがの治療費は基本的に加害者側の保険会社が支払います。
ただこの治療費は、そろそろ治療が終わるだろうという頃に打ち切られます。
むちうちの場合、治療期間は一般的に3ヵ月と言われているので、そのころに打ち切りを通告されることが多いです。
打ち切りの通告に当たっては、保険会社から担当医にそろそろ治療が終わりそうかどうかを確認することが多いようです。
もちろん、この日数以上治療をしてはいけないという制限があるわけではないので、たとえ治療費を打ち切られても治療を継続することは可能です。
ただしその場合は、治療費を自己負担するか、後から加害者側に請求するかになります。
後から加害者側に追加の治療費を請求しても、必ずしも請求が認められるとは限らないという点には注意が必要です。
Q. リハビリも通院日数に含まれますか?
A. 基本的に症状固定前であれば含まれます。
リハビリでの通院は、症状固定前であれば、通院日数に含まれ、入通院慰謝料や治療費の対象となります。
(※症状固定:これ以上治療を続けても大幅な回復は見込めないとして治療が終了されること)
ただし、基本的には病院でのリハビリに限ります。
整骨院でのリハビリは、正確には医療行為として認められないため、通院日数の対象にはならない場合が多いです。
症状固定を過ぎてからのリハビリは、基本的には自費で行うことになります。
しかし場合によっては、リハビリを継続しなければ筋肉が硬直する、症状が悪化するというように、現状維持のためにリハビリが必要な場合があります。
そうした場合は、症状固定後のリハビリであってもその費用を加害者側に請求することができます。
通院日数や通院期間は、ただ単に通院した日数・期間として見られるだけではなく、本当に治療が必要だったのか、本当にこれ以上治療をしても回復しないのかなどを判断する要素の一つとしても見られます。
また、賠償金額を左右する要素でもあるため、非常に重要です。
ポイントを押さえないまま通院していると賠償請求で不利になる可能性もありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
通院後の後遺障害等級認定や示談交渉のサポートも致します。
アトム法律事務所では、LINE・電話無料相談を行っています。
お気軽にご連絡ください。

(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士